20代若いうちにとっておいたほうが将来にむけて難関資格をとっておいたほうが後悔がありません。
年齢が重ねるにつれて難関資格はむずかしくなるものです。しかし20代であれば何度もチャレンジができます。
 シバッタマン
シバッタマン20代前半後半若いうちに取るべきやるべき難関資格を説明いたします。

- シバッタマン
- 精神障害者保健福祉手帳 保持者
- npo法人発達障がい者を支援する会(チームシャイニー)
- 退職代行で40歳で会社を退職し就労移行支援へ
- 氏名:柴田義彦
- 退職代行&就労移行支援、ITの執筆
- 妻と6歳の子供がいて住宅ローン・教育費に必死
- うつ病で休職経験多数
- 経歴・連絡先情報はプロフィールに表示
関連記事:【40代からでも取っておきたい資格】食いっぱぐれなしの国家資格/転職に役立つ資格
関連記事:【30代人生やり直し資格】女性男性人生逆転で人生変わる国家資格
【若いうちに取るべき資格】20代後半逆転資格?20代のうちにやるべきこ 資格!男性女性
20代前半後半若いうちに取るべきやるべきこと難関資格目的1・専門性やスキルを証明できる
自分が将来どうなりたいのか目標を決め、その目標に辿り着くために必要な資格を判断することで、キャリアアップにつながります。
 シバッタマン
シバッタマン20代女性男性が将来どうなりたいのか目標を決め、その目標に辿り着くために必要な資格を判断することで、キャリアアップにつながります。
お金になりそうな資格をむやみに取得するのではなく、あくまでも自分が目指す目標・ゴールに必要な資格を選定し取得することが大切。
難関資格を保有していれば、合格するに至った努力も合わせて評価されます。
20代前半後半若いうちに取るべきやるべきこと難関資格目的2・給料アップにつながる
 シバッタマン
シバッタマン20代女性男性だやアラサー女性男性が転職をするにしてもしないにしても会社の福利厚生として資格手当がある会社が多いです。
その資格がないと担当できない業務がある場合は、資格取得によって毎月の給与に「プラス数千円~数万円」という形で反映される形式です。資格がなくても業務に差し支えないが、スキルアップのために資格取得を推奨している場合などで、合格時にお祝い金として一時金を渡す形式。
受検費用や教材費を企業が負担してくれるかどうかも、任意の制度内容なので企業によって異なります。
20代前半後半若いうちに取るべきやるべきこと難関資格3・専門知識をさらに高めるため
 シバッタマン
シバッタマン20代が仕事に関わる専門分野についての国家資格を取得すると、専門知識を身につける機会につながります。
また、企業の事業活動に関わる資格を取得すると、キャリアアップにつながりやすくなります。
結果として資格内容によっては管理職に昇進したり、責任のある仕事やポジションを任されたりするなど、さまざまな可能性がうまれるでしょう。
【若いうちに取るべき資格】20代後半逆転 資格のおすすめ
20代若いうちに取るべき資格1・宅地建物取引士
宅建士は「宅地建物取引士」の略称で、毎年20万人前後の受験者数を誇る最大規模の国家資格です。
 シバッタマン
シバッタマン宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者です。
宅地建物取引業者(一般に不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家となります。
宅地建物取引士の仕事内容について
 シバッタマン
シバッタマン宅地建物取引士の仕事内容は、以下の通りです。
・宅地建物の取引の契約締結の際に、重要事項説明をする
・宅地建物の取引の契約締結後に交付する書類に、署名や押印をする
このふたつの業務は、宅建の資格を持っている人しか行うことができません。
さらに下記の仕事もあります。
・土地や建物の売り出しをしたい人の手助けをする
・土地や建物の購入をしたい人、借りたい人の要望にあった不動産を探し、紹介する
・土地や建物の売主・買主の仲介をし、契約までの段取り、契約のサポートを行う
・土地や建物を貸したい人・借りたい人の仲介をし、賃貸契約までの段取り、契約のサポート
転職に役立つのか
不動産業界関連への就職や転職には特に大きなメリットとなります。
それ以外にも建築業界、金融業界などへの就職・転職活動でも有利になることがあります。昨今、全国に支店を展開する大手企業やIT業界でもニーズが高まってきています。
資格を持つことで、社会的に一定水準以上の知識を有することを証明することができます。また、昇格の宅建の取得を必須条件とする企業もあります。さらに、独立開業やキャリアアップにもつながることは、大きなメリットといえるでしょう。不動産鑑定士や司法書士などの資格と宅建を組み合わせることで、業務の幅を大きく広げられるチャンスもあります。
企業にもよりますが、毎月の給与のベースが5千円~5万円アップすることもあります。合格は一生有効ですから、資格を取得して損はありません。
受験資格について
 シバッタマン
シバッタマン宅建試験には受験資格がありません。 年齢・国籍・学歴・実務経験に関係なく、誰でも受験できます。 つまり、どんな人にも平等にチャンスが与えられ、実力があれば合格できます。
| 年度 | 合格基準点 |
|---|---|
| 2021年(令和3年度12月試験) | 34点 |
| 2021年(令和3年度10月試験) | 34点 |
| 2020年(令和2年度12月試験) | 36点 |
| 2020年(令和2年度10月試験) | 38点 |
| 2019年(令和元年度) | 35点 |
| 2018年(平成30年度) | 37点 |
| 2017年(平成29年度) | 35点 |
| 2016年(平成28年度) | 35点 |
| 2015年(平成27年度) | 31点 |
| 2014年(平成26年度) | 32点 |
| 2013年(平成25年度) | 33点 |
原則として12月の第1水曜日、または11月の最終水曜日に都道府県ごとに発表されます。また、合格発表は「不動産適正取引推進機構」のホームページでも、合格者受験番号・合否判定基準・試験問題の正解番号を確認することが可能です。
宅地建物取引士の給料について
企業に勤務した場合、宅建士の平均年収は約470万円~626万円程度です。企業規模・役職などによっても幅があります。企業規模ごとの平均年収は、大企業の場合は一般的に626万円、中規模の企業の場合は518万円、小規模の企業の場合は470万円となります。
20代若いうちに取るべき資格2・看護師
国家資格を必要とする看護師は、厚生労働大臣の免許を受けることが前提です。傷病者だけでなく、出産後間もなくの女性(じよく婦)の世話も看護師の担当となります。また医師の診療補助にあたり、医師の右腕となって医療に関わる重要なポジションです。
 シバッタマン
シバッタマン厚生労働省では下記の通り定義されています。
「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
引用元:厚生労働省
看護師の仕事内容について
 シバッタマン
シバッタマン看護師のお仕事は医師の診察にもとづき、診療や治療の補助を行い、病気やケガなどで不自由な生活を送る患者さんに対して、看護を提供します。
- 具体的には、問診や各種検査、点滴や注射、食事・排泄の補助、患者移送、検温や入浴の介助、体位交換、記録、巡回、ベッドメイキングなど。 患者の症状を正確に把握し、医師に報告するのも仕事となります
医師の補助だけではあります。
高度化・専門化する医療体制のなかで、患者さんと医療スタッフ間のコミュニケーションを円滑にし、患者さんの相談や指導などといった心のケアも看護師の大切な仕事です。
転職に役立つのか
 シバッタマン
シバッタマン資格を取得するのは困難なものの、人手不足な看護師の世界では、20代での転職もさほど難しくありません。
この時期を逃して50代に突入してしまうと転職市場も一気に変化するので20代での転職は「最後まで働く勤務先を決める活動になるかもしれない」という意気込みが必要になるでしょう。
しかし、今後のキャリアについて考える際は、個人ごとに事情が異なってくるので自分に合わせたキャリア選択が必要となってきます。
受験資格について
 シバッタマン
シバッタマン最も一般的なのは、高校を卒業後に以下のような看護師養成校に通うルートです。ただ、20代でも十分に間に合います
・4年制大学
・3年制短期大学
・3~4年制専門学校
通常の高校ではなく5年一貫性看護高校に通えば、最短20歳で受験資格を得ることもできます。最初の3年間を終了すれば高校卒業資格が与えられるため、その時点で大学に進学することも可能です。
年を重ねてから、看護師の資格取得を目指す人が増えている。全国の看護系大学や専門学校に入学した40歳以上の人は、2006年の698人から16年には1384人にほぼ倍増(厚生労働省調べ)。子育てが一段落して経済的自立を目指すが多い。団塊の世代がすべて75歳以上となる25年には深刻な看護師不足が懸念され、少子化で若い世代が先細る中、医療現場の期待も高い。
引用元:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/341643/
看護師の給料について
30~34歳の看護師の年収は476.9万円、35~39歳は476.4万円と差はほとんどありません。
しかし、40~44歳になると平均年収は506.4万円に跳ね上がり、45~49歳では525.9万円と更に増えていきます。
| 年代(歳) | 平均年収 (万円) | 平均月収 (万円) | 毎月の手取り額目安 (万円) |
| 30~34 | 460.6 | 32.4 | 25.9 |
| 35~39 | 475.2 | 33.2 | 26.5 |
20代若いうちに取るべき資格3・登録販売者
薬剤師のいない店舗でも登録販売者がいれば医薬品を販売できるようになったことから、ドラッグストア以外の一般の小売店──スーパーやホームセンター、家電量販店などでも医薬品の取り扱いが増えました。
 シバッタマン
シバッタマン登録販売者とは、2009年の改正薬事法(現在の薬機法)の施行により誕生した一般用医薬品(市販薬)の販売に必要な専門資格です。
登録販売者とは、2009年の改正薬事法により誕生した『かぜ薬や鎮痛剤などの一般用医薬品(第2類・第3類に限る)販売を行うための専門資格』です
登録販売者は一般用医薬品のうち第2類医薬品と第3類医薬品を販売することができます。
ほぼすべての品目を取り扱うことができます
登録販売者の仕事内容について
登録販売者はドラッグストアやスーパー・コンビニで働くのがほとんどです。これらの職場では医薬品の相談・アドバイスの他に店舗スタッフとしての仕事も任されます。
接客、レジ会計、品だし、薬の管理・発注など一般的な店舗運営の他、ドラッグストアでは花粉症薬など季節の商品の売り場づくりなども行います。
 シバッタマン
シバッタマン登録販売者の仕事内容といえば、市販薬と呼ばれる第2類・第3類医薬品の販売です。
来店されたお客様にヒアリングをして症状や使用目的から適切な薬選びをお手伝いするのが登録販売者の重要な仕事です。
なかにはアレルギーがある方や、以前の薬が体に合わなかったなどというお客様もいます。
そういった方は一歩間違えれば重篤な事故につながりかねないため、登録販売者にはしっかりとした知識が必要です。
場合によっては生活習慣のアドバイスや医療機関の受診を勧めるケースもあります。
転職に役立つのか
 シバッタマン
シバッタマン薬剤師が慢性的に不足していることからも登録販売者に対する需要は多く、制度開始から2021年3月末までに延べ30万人以上の方が登録販売者試験に合格しています
薬剤師が薬の調剤から販売まで幅広く携わる医薬品の専門家なのに対して、登録販売者はあくまで医薬品の“販売”に関する専門資格です。
| 登録販売者 | 薬剤師 | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 薬機法 | 薬剤師法 |
| 資格の位置付け | 都道府県知事の登録 | 厚生労働大臣の免許 |
| 受験資格 | とくになし | 薬学部(6年制)卒 |
| 主な業務 | 医薬品の販売 | 医薬品の調剤 医薬品の販売 |
| 販売できる一般用医薬品 | 第2類医薬品 第3類医薬品 | 第1類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品 |
受験資格について
 シバッタマン
シバッタマン資格取得するためには、年1回各都道府県で実施されている『登録販売者試験』で合格する必要があります。昨年(2021年)の登録販売者試験の合格率は全国平均49.0%でした。
注意すべきは、都道府県ごとに試験日や申込期日が異なることです。下記ページで直近の試験について詳しく解説しています。登録販売者試験は各都道府県ごとに実施されており、試験問題も各都道府県によって異なります。
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| 受験資格 | 学歴・実務経験問わず受験可能 |
| 問題数 出題範囲 | 問題数:120問 【内訳】 第1章:医薬品に共通する特性と基本的な知識(20問) 第2章:人体の働きと医薬品(20問) 第3章:薬事に関する法規と制度(20問) 第4章:主な医薬品とその作用(40問) 第5章:医薬品の適正使用と安全対策(20問) ※出題範囲・問題数は全国共通ですが、地域によって午前・午後で出題項目が異なる場合があります。試験案内(受験の手引き)や過去問などでチェックしてみてください。 |
| 試験実施日 | 2021年8月25日~2021年12月12日 ※各都道府県により異なります。 。 |
| 受験場所 | 各都道府県の指定場所 |
| 受験料 | 12,800円~18,100円 |
| 合格基準 | 総出題数に対して7割程度の正答、かつ出題項目全て(5項目)で3.5割以上 ※一部地域では4割以上の正答 |
| 合格率 | 49.0%(2021年度全国平均数値) ※各都道府県により異なります。 |
| 合格発表日 | 2021年9月28日(火)~2022年1月19日(金) ※各都道府県により異なります。 |
登録販売者の給料について
 シバッタマン
シバッタマン正社員の登録販売者として働く場合の給料は20万円ほどが相場となります。年収に直すとおよそ300~350万円ほどで、日本の平均年収よりもやや低い傾向にあります。
パート・アルバイトでも有資格者には資格手当がつくことが多いです。その場合、数百円が時給に上乗せされるのが一般的です。資格手当は5000円~2万円ほどが一般的です。正社員の場合はボーナスが夏と冬にそれぞれ2ヶ月分支給されることが多いです。
| 業種 | 正社員 |
|---|---|
| 薬局 | 【資格手当あり】 20万円~27万円 年収320万円~430万円 |
| 薬店・ドラッグストア | 【資格手当あり】 月給19.5万円~25万円 年収300万円~400万円 |
| 【未資格者】 172,000円以上 | 【未資格者】 1,000円~ |
| コンビニエンスストア | 【資格手当あり】 月給20万円~35万円 年収300万円~560万円 |
| 【未資格者】 18万円~ | 【未資格者】 960円以上 |
国内で働く場合、1コマあたりの単価は約1,500~2,000円、正社員なら月収は20万円以上です。
一方、海外の場合、国によって物価が異なるため一概にはいえないものの、働く国の給料水準と比較して同程度か少し高いくらいの給料である場合が一般的です
20代若いうちに取るべき資格3・行政書士
行政書士にはそういった受験資格の制限がないので、誰でも受験できます。許認可申請のプロの視点でスムーズに行なわれるよう、相談から書類作成、提出代理までを行政書士が行ないます。
司法試験ならロースクール卒業、税理士試験なら簿記1級、社会保険労務士なら大卒以上、など、様々な受験資格が定められています。
 シバッタマン
シバッタマン行政書士は、行政手続を専門とする法律家です。但し、行政書士が独占する業務に加え、他の資格で独占されていないものも仕事とすることができるため、非常に広い業務範囲を持ちます。
行政書士は会計記帳、決算、財務諸表の作成など会計業務に携わることができます。 中小企業に対して法務的観点から幅広いアドバイスが行えます。
引用元:https://gyosei-shiken.or.jp/
行政書士の仕事内容について
事業を経営する人にとって、公官署に提出する書類は煩雑で面倒なものが多く、自力で手続きするには時間がかかります。 行政書士は、そんな事業者に代わって書類を作成し、提出なども代行する事が出来るパートナーとなります。
官公署に申請する書類は膨大なものになります。
 シバッタマン
シバッタマン提出書類を作成したり、申請のために必要となる公的証明書などを収集して、すべての書類が揃ったら役所に提出します。 たいていの書類は手続きの段階ごとに提出期限が定められているため、依頼者の希望するスケジュールによっては、急いで作業を進めなければなりません。
転職に役立つのか
一般企業に勤めていたなどで社会人としての経験や人脈がすでに培われている人の場合、合格後すぐに独立の準備をする人もいます。
合格後すぐの独立は無計画でいきなりするのではなく、だいたい半年から1年ほどの期間は開業のために必要な資金を貯めたり、開業に必要な知識を身に着けていくのがよいでしょう。
受験資格について
行政書士とは、主に行政への許認可申請が必要となる場合に提出する書類の作成、官公署に届ける書類に関する相談業務などを行う法律の専門家です。
同じように、法律の専門家とされる士業には、税理士や社労士、司法書士などがあります。 そのなかでも行政書士はほかの士業と比較して、幅広い業務範囲が特徴です。
 シバッタマン
シバッタマン行政書士となる資格を有する者が行政書士となるためには、日本行政書士会連合会が備える行政書士名簿への登録を受けなければなりません。
行政書士に合格するまでの平均受験回数は2回前後と言われています。
そのため 行政書士は2~3年かけて合格を目指すべき資格 であると言えます。 ただし平均受験回数が2回前後なのであって、1発で合格する人もいれば4年程かかる人もいます。 5年以上かかる人は滅多にいませんが、1~3回受験して合格する人が多いのが現状です。
行政書士なら東京法経学院の行政書士コースへ
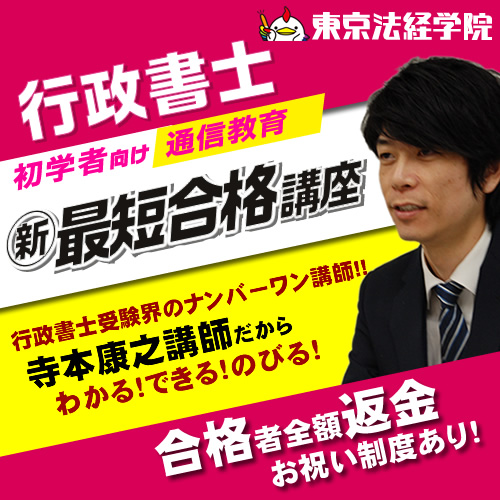
東京法経学院は、難関資格の対策講座を提供する老舗の予備校です。司法書士や行政書士などの講座があり、合格実績や人気が抜群です
 シバッタマン
シバッタマン通学が難しい方にも通信講座をご用意していますので、どんな方にも最適な学習方法が見つかります
【自信を持って挑戦しよう】
東京法経学院で確かな知識と技術を身につけ、自信を持って行政書士試験に挑むことができます。さらに、2023年度の公開模試も2回実施されるので、試験対策を万全に整えることが可能で
東京法経学院は今なら合格者返金お祝い制度を実施
今ならなんと合格者全員返金お祝い制度があります!
効率的に学習ができる総合答練コースを活用し、短期間で試験に合格しましょう。
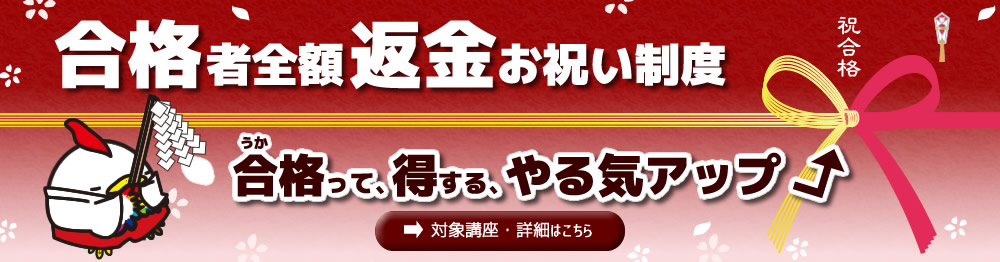
| 対象講座 | 行政書士新・最短合格講座 |
| 対象タイプ | [総合コース]基礎力総合編 +合格直結答練2023 |
 シバッタマン
シバッタマン東京法経学院の行政書士コースで、確かな知識と技術を身につけ、資格試験合格への道を切り開きましょう。今すぐお申し込みください!
\ 合格者全額返金お祝い制度あり /
20代若いうちに取るべき資格4:介護リハビリセラピスト

介護リハビリセラピストは、高齢者の身体機能の回復や維持を目的として、マッサージやストレッチ、運動療法などのリハビリテーションを行うセラピストです
セラピストとは、専門的な知識や技術に基づいて心身を癒したり、治療する人のことを指します。 「療法士」や「治療士」と言うこともあります。
介護リハビリセラピストは、セラピストの中では、介護に特化したセラピストと言えます。
高齢者の生活の質を向上させることを目的としたこれから必要とされる仕事です。高齢化社会の進展により需要が高まっている職業です。
転職に役立つのか
介護リハビリセラピストは、高齢者の健康に貢献できる資格であり、介護施設や高齢者向けのマッサージサロンなど、転職先はたくさんあります
一般的には介護職員、看護師、セラピスト、エステティシャン、主婦の方の受講が多いといわれています。
高齢者の健康を維持・改善するためのアドバイスや運動指導なども行うことができるため、介護福祉士や看護師などの資格を持っている方よりも、転職先の選択肢が広がります。
介護に興味のある方や、マッサージ師として働きたい方は、介護リハビリセラピストの資格取得を検討してみてはいかがでしょうか。
介護リハビリセラピストの給料は?
 シバッタマン
シバッタマン介護リハビリセラピストは、主に介護施設で働いています。その他にも、高齢者向けのマッサージサロンや整形外科などでも働いています。また、独立開業することも可能ですね。
介護リハビリセラピストの給料は、勤務する施設や地域によって異なります。上記でもお伝えしましたが、高齢者の生活の質を向上を目的としているため介護施設や病ん、独立など様々な勤務が考えらえます。
平均して年収300万円~400万円程度です。経験やスキルが豊富な場合は、年収500万円以上になることもあります。
上記のため、高齢化社会の進展により需要が高まっている職業であり、今後も給与の上昇は予想されています。
仕事内容について
介護リハビリセラピストの特徴は、以下のとおりです。
| 仕事内容 | 説明 |
|---|---|
| 身体機能の回復や維持を目的としたリハビリ | マッサージやストレッチ、運動療法などの手技を用いて、高齢者の身体機能を回復や維持する。 |
| 身体機能や状態に合わせてリハビリテーションプログラムを作成・実施 | 高齢者の身体機能や状態を把握し、その人に合ったリハビリテーションプログラムを作成・実施する。 |
| 高齢者や家族へのリハビリテーションや教育・指導を行う。 | 高齢者やその家族に、リハビリテーションの目的や効果、方法などを説明し、理解を深めるように指導する。 |
受験資格について
介護リハビリセラピストの受験資格は、介護系の資格や経験がなくても受験することができます。女性をイメージすることが多いかもしれませんが、介護リハビリセラピスト資格を取得している3割は男性です。
介護リハビリセラピスト協会が実施している講座を受講し、修了試験に合格する必要があります。1回目の試験での合格率は約94%です
講座は通信講座と通学講座の2種類があり、通信講座は受講期間が約6ヶ月、通学講座は受講期間が約3ヶ月です。修了試験は筆記試験と実技試験があり、どちらも合格する必要があります。
介護リハビリセラピスト通信講座の受講者様の90%以上がお仕事をされています。また通信講座でもオンライン講座を受けられます。
\ その他通信講座よりも圧倒的の低価格 /
介護リハビリセラピストは、高齢者の健康に貢献できるやりがいのある仕事です。介護に興味のある方や、マッサージ師として働きたい方は、介護リハビリセラピスト通信講座の受講を検討してみてはいかがでしょうか。
通信講座費用は下記です。一括払いだととても安価な通信講座です
| 支払い方法 | 受講料 |
|---|---|
| 一括払い | 29,800円 |
| 分割払い | 1,444円 × 24回 |
| 通常受講料 | 44,000円 |
※お支払いはクレジットカード払い(一括・分割・リボ)や銀行振込(一括のみ)です。
20代若いうちに取るべき資格:司法書士
超難関の資格として知られる司法書士です。だからこそ20代の若いうちに取っておきたい司法書士です。
 シバッタマン
シバッタマン司法書士は、行政機関に提出する書類の作成や審査請求を行う職種です。作業には法律に関する専門知識が必要となるため、資格を有する司法書士が個人や法人などから依頼を受け、代行します。
司法書士は単に手続きを進めるだけでなく、依頼者から法律に関する相談を受けることも多いです。依頼者にとって必要な手続きを、適切かつスムーズに進めることが司法書士の役割です。
司法書士と弁護士では、扱える業務の範囲に違いがあります。弁護士が法律に関する業務のすべてに対応できるのに対し、司法書士が対応できるのは書類作成や登記など一部の業務に限られているのです。
司法書士の仕事内容について
司法書士は、法務局、裁判所、検察庁などへ提出するための書類を作成します。特に、登記や供託の手続きを依頼されることが多いです。また、審査請求の手続きを依頼者の代理で行う場合もあります。
登記業務
司法書士の仕事のなかで最も多いのは、登記手続きです。登記手続きには、大きくわけて不動産と商業(法人)の二つがあります。
供託業務
司法書士は供託業務を行うことも多いです。供託とは、有価証券や金銭を供託所である法務局に預け、それらを渡すべき相手に適切に分配する手続きのことです。
書類作成
司法書士は、専門知識が必要な行政機関、法務局または地方法務局へ提出するための書類を作成するだけでなく、依頼者が手続きを滞りなく進めるためのアドバイスも行わなければなりません。また、検察庁や裁判所への申立書の提出する書類の作成なども行います。
訴訟代理・支援
認定司法書士であれば、訴訟の代理や支援も行えます。簡易裁判所での手続きにおいて、司法書士は依頼者の代理人として活動することが可能です。
企業法務
司法書士は、企業法務を対象とした活動も可能です。企業法務とは、企業の運営にかかわる法律上の規制を把握し、トラブルを防いだり解決したりする業務です。
相続・成年後見業務
司法書士は相続に関する相談も受けられます。正式な遺言書の作成や、相続による不動産の移転登記の手続きも可能です。また、司法書士は、成年後見制度を利用するための手続きやサポートもできます。
転職に役立つのか
 シバッタマン
シバッタマン司法書士試験に合格した有資格者の場合は、特別な実務経験は必要なく、若いうちに取っておきたい資格ですね。
司法書士になる道筋として一般的なのは、司法書士試験に合格し必要な研修を受けてから、各都道府県の司法書士会に登録して活動することになります。
実務で身につくスキルには、不動産登記や商業登記などの登記業務、様々な相談事より発生する相談業務やこれにより派生した裁判事務などのほか、会社法を専門的に学習していることで、その知識を活かした企業法務コンサルティングなどもあります。
認定司法書士の資格を得れば、一定の条件を満たした簡易裁判において、代理人として法廷に立つこともでき、自身の業務の幅を拡げることができます。
参考元:法務省引用書士試験
受験資格について
 シバッタマン
シバッタマン超難関の資格として知られる司法書士。意外なことに、学歴や経験に関係なく誰でも資格試験が受けられます。令和3年度司法書士試験合格者の平均年齢は41.79歳。 30代・40代を中心に合格者が多いのが特徴です。
また、受験回数にも制限はなく、合格するまで何度でもチャレンジが可能です。 司法書士試験は、「筆記試験」「口述試験」のふたつに分かれて行われます。
司法書士の給料について
40代の場合は、510万~710万円程度です。40代になるとベテランの領域となり、年収額もそれに付随した金額になります。
企業勤務の司法書士の場合、平均年収は250万~400万円程度になります。士業であることや超難関試験を突破することのイメージからすれば、低い金額に思えるかもしれません。
司法書士として経験を積んでいけば、給料も徐々に上がっていく傾向にあります。また、大型事務所や有名事務所で経験を積めば、平均年収が500万~700万円程度になることもあります。
 シバッタマン
シバッタマン40代の場合は、510万~710万円程度です。40代になるとベテランの領域となり、年収額もそれに付随した金額になります。50代の場合は、650万~760万円程度になります。50代ともなると、好収入と呼ばれる年収になることがわかります。
司法書士は東京法経学院の司法書士コースへ
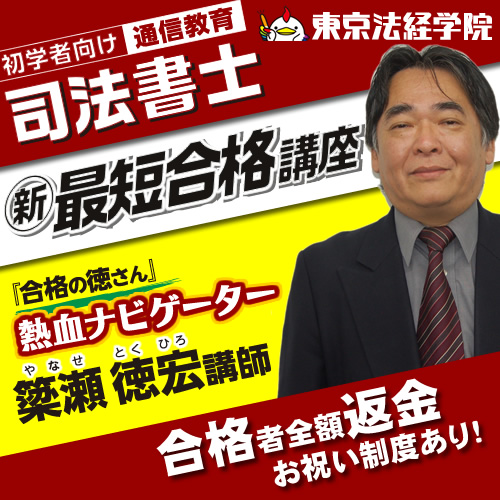
あなたの夢を叶えるために、東京法経学院の司法書士コースに参加しましょう!高い合格実績と人気を誇る東京法経学院は、難関資格試験の対策講座を提供する老舗の予備校です。
通学が難しい方も安心して学べる通信講座が用意されています
 シバッタマン
シバッタマン通学が難しい方も安心して学べる通信講座が用意されています
東京法経学院は今なら合格者返金お祝い制度を実施
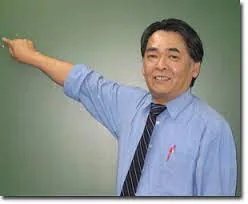
今だけの特別割引もあります!
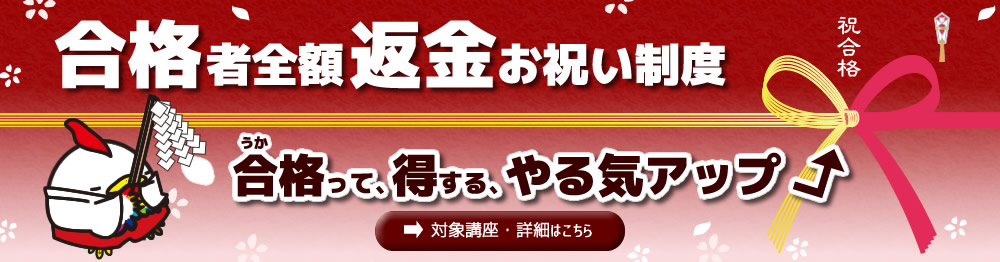
東京法経学院で確かな知識と技術を身につけ、自信を持って司法書士試験に挑むことができます。さらに、2023年度の公開模試も2回実施されるので、試験対策を万全に整えることが可能です
| 対象講座 | 簗瀬徳宏の司法書士 新・最短合格講座2024 |
| 対象タイプ | 総合コース |
| 対象試験年度 | 2024年度試験 |
 シバッタマン
シバッタマン東京法経学院の司法書士コースで、確かな知識と技術を身につけ、資格試験合格への道を切り開きましょう。今すぐお申し込みください!
\ 合格者全額返金お祝い精度あり /
あなたの夢を叶えるために、今こそ行動を起こしましょう。東京法経学院の司法書士コースに参加し、資格試験合格への道を切り開く一歩を踏み出す勇気を持ちましょう。
まとめ:【若いうちに取るべき資格】20代後半逆転資格?20代のうちにやるべきこと 資格!男性女性
いかがでしたでしょうか。
今回の記事は【若いうちに取るべき資格】20代後半逆転資格?20代のうちにやるべきこと 資格!男性女性 についておつたえしました。
年齢をかさねるたびに保守的に考えがあり、ライフサイクルがかわってきます。難関資格は若いうちにとっておいたほうが良いと考えられますね。







コメント